奈良県と三重県の県境に位置する大台ヶ原は、その圧倒的な標高(1,695m)と、周囲に光害が少ないという絶好のロケーションから、満天の星空を眺めるには最高の場所です。特に、夏の夜空を彩る雄大な天の川は、息をのむほどの美しさ。
この記事では、
「大台ケ原で夜登山」を計画している方や、車でアクセスして大台ヶ原 駐車場から手軽に星空を眺めたい方のために、星景写真家が実践する「いつ」「どこで」「どうやって」撮影するかを徹底的に解説します。夏の天の川が最も美しく見える時期(2月〜9月)ごとの見え方から、おすすめの撮影スポット、具体的な登山計画、必要な装備、そして撮影後の疲れを癒やしてくれる近隣の温泉情報まで、あなたの星空撮影を成功させるための完全ガイドです。
おすすめの星空スポットの記事はこちら💁
大台ヶ原の魅力:標高とロケーションが育む星空
標高1,695mが生み出すクリアな空気
大台ヶ原 標高は、最高峰の日出ヶ岳で1,695m。この高い標高は、平地では見られないような澄み切った空気をもたらします。湿気が少なく、塵や埃の影響を受けにくい上空では、星の瞬きがより鮮明に見え、写真に撮った際にもクリアで美しい星空を写し出すことができます。
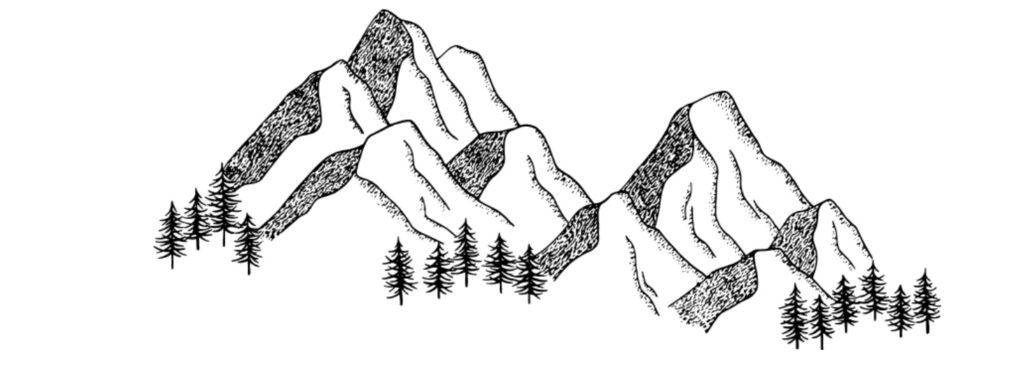
光害の少なさ
大台ヶ原は、周辺に大きな市街地がなく、人工的な光の影響(光害)が非常に少ないのが特徴です。特に南の方角は、人工の灯りがほとんどなく、天の川の中心部を撮影するのに最適な環境が整っています。三重県 星がきれいに見える場所としても有名で、遠方からも多くの天文ファンが訪れる理由の一つです。
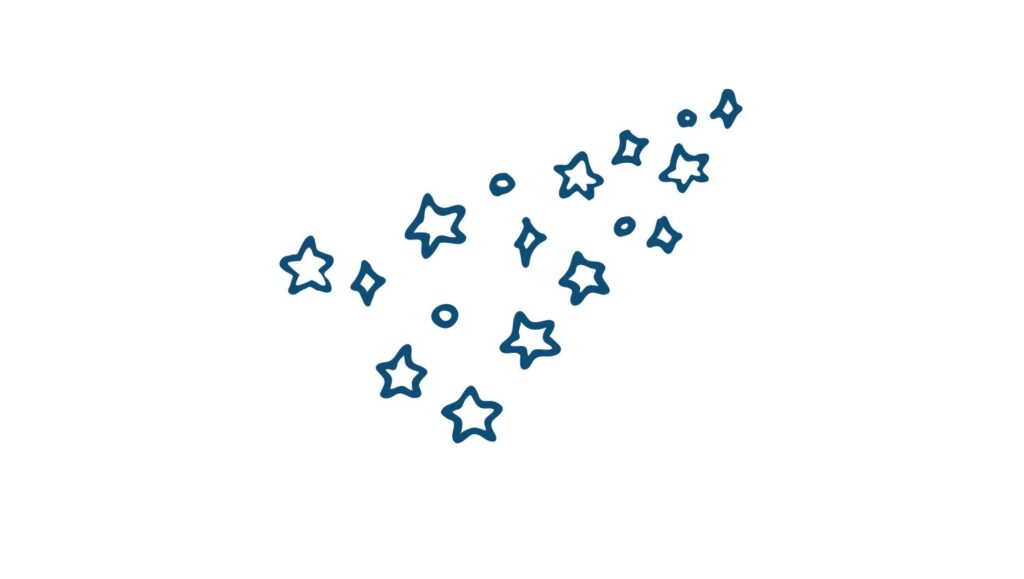
大台ヶ原で天の川を撮る:季節別・時間帯別アドバイス
夏の天の川は、一年中同じように見えるわけではありません。時期や時間帯によって、空での位置や見え方が大きく変わります。ここでは、天の川を効率よく撮影するための具体的な計画を立てましょう。
2月〜4月(明け方の天の川)
この時期の天の川は、明け方の東の空に横たわるように現れます。夜半はまだ地平線の下に隠れており、午前3時頃から徐々に姿を現し、夜明け前に最も高く上がります。冬の星座と夏の天の川を同時に収めることができる、特別な時期です。ただし、この時期はまだ冷え込みが厳しいため、万全の防寒対策が必要です。
- 撮影時間帯:午前3時〜夜明け前
- 方角:東の空
- 特徴:地平線から立ち上がる天の川と、明け方の景色を組み合わせた構図が狙えます。
5月〜7月(立ち上がる天の川)
春が過ぎ、夏が近づくにつれて、天の川は夜半、南の空に斜めに立ち上がるようになります。日付が変わる前の早い時間帯から撮影が可能です。天の川の中心部が空高くに位置するため、より濃く、鮮明に写し出すことができます。新月に近い日を選ぶと、一層美しい天の川を堪能できます。
- 撮影時間帯:23時〜夜半
- 方角:南の空
- 特徴:天の川の中心部を大きく、力強く写したい場合に最適です。

8月〜9月(直立する天の川)
夏本番から秋にかけては、天の川が最も見やすい時期です。日没後、空が暗くなり始めた直後から、天の川が頭上を直立するように輝きます。深夜まで粘る必要がないため、比較的初心者にもおすすめです。夏の夜空を象徴する、最も賑やかな天の川を楽に撮影できます。気温も比較的穏やかなので、撮影しやすいでしょう。
- 撮影時間帯:日没後〜深夜
- 方角:南の空(徐々に西へ移動)
- 特徴:日没後のマジックアワーと天の川を組み合わせた、ドラマチックな写真が狙えます。
このように、5月~9月が最も撮影しやすく、7~8月は特に天の川が頭上〜直立に近く見えるため、構図がダイナミックになります。2~4月は明け方主体となりますので、前夜入り・車中泊などを使って時間を確保するとよいでしょう。

撮影スポット徹底ガイド:大台ヶ原の絶景と星空を一枚に
大台ヶ原には、星景写真に最適なユニークな撮影スポットが点在しています。それぞれの場所の特徴を理解して、最高の構図を見つけましょう。
撮影時には地平線近くを入れたいなら東・南東方向に視界が開けている場所を探すこと、そして周囲の木や岩を前景に入れることで星景らしい写真になることを念頭に置くとよいです。

大台ヶ原ビジターセンター周辺
大台ヶ原 駐車場に車を停めて、すぐに撮影に取り掛かれるのがこのエリアの最大の魅力です。夜間でも比較的安全に移動でき、トイレや休憩スペースもあるため、初心者や家族連れにもおすすめです。周囲の木々やビジターセンターの建物を前景にすることで、奥行きのある構図が作れます。
- アクセス:駐車場からすぐ
- 利点:手軽さ、安全性、設備の利用が可能
- 構図のヒント:駐車場周辺の広場や、ビジターセンター前の芝生から、広い空を写し込む。
日出ヶ岳(ひでがたけ)山頂
ビジターセンターから片道約40分の登山で到達できる最高峰です。夜間はヘッドライトが必須ですが、木道が整備されているため比較的歩きやすいルートです。山頂の展望台からは360度の大パノラマが広がり、特に東の空が大きく開けているため、天の川と日の出を組み合わせた壮大な写真を狙うことができます。雲海が発生した日には、雲の海に浮かぶ星々という幻想的な光景に出会えるかもしれません。
- アクセス:ビジターセンターから徒歩約40分
- 利点:360度の大パノラマ、日の出撮影も可能
- 構図のヒント:展望台の東側から、天の川と日の出を一つのフレームに収める。

大蛇嵓(だいじゃぐら)
ビジターセンターから片道約1時間半、大台ヶ原の中でも最もスリルと絶景が楽しめる場所です。断崖絶壁の上に突き出た岩場からは、圧倒的なスケールの景色が楽しめます。星景写真の構図としても非常に魅力的ですが、夜間の通行は危険を伴います。ヘッドライトが必須で、風が強い日は特に注意が必要です。安全を最優先し、慎重に行動しましょう。
- アクセス:ビジターセンターから徒歩約1時間半
- 利点:大迫力の構図が撮れる、唯一無二の絶景
- 構図のヒント:岩場の突端に立つ人物をシルエットにし、満天の星空を背景にする。
夜間の登山計画とアクセス:大台ヶ原 駐車場までの道と注意点
大台ヶ原は登山だけでなく、車でのアクセスにも注意が必要です。
アクセス方法:車が基本
大台ヶ原へのアクセスは、自家用車が基本です。東の三重県側、西の奈良県側からそれぞれ道が続いています。いずれも山道を登っていくことになります。
大台ヶ原ドライブウェイの通行規制
大台ヶ原へ続く「大台ヶ原ドライブウェイ」は、例年12月上旬から4月下旬まで冬季閉鎖されます。星空撮影を計画する際は、事前に通行情報を確認しましょう。また、夜間は鹿などの野生動物が飛び出してくる可能性があるため、速度を落として慎重に運転してください。
大台ヶ原駐車場情報
大台ヶ原ビジターセンターの目の前にある駐車場は、約200台収容可能です。夜間も利用できますが、登山や撮影で訪れる人が多いため、特に週末や新月の前後には満車になることもあります。早めの到着をおすすめします。駐車場にトイレはありますが、夜間は使用できない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
夜間登山(ナイトハイク)の注意点
大台ヶ原 夜 登山は、日中の登山とは全く違うリスクを伴います。以下の点を必ず守ってください。
- ヘッドライトは必須:両手が空くヘッドライトを必ず用意し、予備の電池も持参しましょう。
- 道迷い防止:登山ルートは木道が整備されていますが、夜間は道が分かりにくくなることも。事前にルートを頭に入れ、スマートフォンのGPSアプリなどを活用しましょう。
- グループで行動:単独での夜間登山は避け、できるだけ複数人で行きましょう。
- 防寒・雨具:大台ヶ原は日本有数の多雨地帯です。突然の雨や気温の低下に備え、雨具と防寒着は必ず持参しましょう。
撮影モデルプラン:日帰り&宿泊の具体例
あなたの目的に合わせて、具体的なモデルプランを提案します。
日帰りモデルプラン(真夏の直立する天の川を狙う!)
(対象:体力に自信のある方、夜間に帰宅したい方)
- 17:00:大台ヶ原駐車場に到着。ビジターセンター周辺で準備を開始。
- 18:00:日没後、ビジターセンター周辺で星空撮影を開始。夕食を済ませてから、日出ヶ岳へ向けて夜間登山開始。
- 19:00:日出ヶ岳山頂に到着。機材をセッティングし、夜空が暗くなるのを待つ。
- 20:00〜22:00:直立する天の川を撮影。
- 22:30〜:下山開始。駐車場に戻る。
宿泊モデルプラン(星空と日の出を両方楽しむ!)
(対象:じっくりと撮影を楽しみたい方)
- 前日15:00頃:大台ヶ原周辺の宿泊施設にチェックイン。
- 18:00〜:夕食を済ませ、車で大台ヶ原駐車場へ移動。
- 19:00〜:日出ヶ岳へナイトハイクを開始。
- 20:00〜深夜:山頂や道中で天の川を撮影。
- 深夜:一度宿泊施設に戻り、仮眠。
- 翌日3:00:再び大台ヶ原へ。日の出撮影に備える。
- 早朝:日の出と、明け方の横たわる天の川を撮影。
モデルプラン A:8月中旬の夕方~深夜前
目的:8月に、夜21時〜23時ごろに天の川が直立気味に見える空を撮る+前景として展望所(大蛇嵓など)を入れた構図を狙う。
モデルプラン A:8月の夜空狙い
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 前日(A日) | 午後:現地へ移動 → 「心・湯治館」など近隣宿に前泊(ロケーションを整える) 夜:天気予報と月齢を確認。新月期か月没時間を基準に。 |
| 撮影日(B日) | 早めに夕食後、20:00頃宿を出発 → 大台ヶ原駐車場へ移動。 駐車場付近または少し歩いて良い前景のあるスポット(日出ヶ岳展望台か大蛇嵓方向)へ。 2025年8月中旬なら、日没後すぐでも南東方向に星や天の川が上がってくるので21時ごろから撮影開始。 21:00〜23:00 星空+前景撮影(大蛇嵓のシルエットなどを含める) → 氷点下にならないよう防寒準備。 深夜前に宿または車中泊場所へ戻る。 |
| 翌朝 | 明け方の撮影(2月など春先ならここが重要だが、8月は夜の方が良いため状況次第) 朝日の撮影も可能(例:日出ヶ岳から) 午前中はハイキング → 正木ヶ原、牛石ヶ原などで明るくなってきた星の影響を残す構図を探す。 |
モデルプラン B:4月の明け方狙い
目的:4月に、明け方に東の地平線近くに横たわる天の川を撮る。前景に日出ヶ岳か樹林のシルエットを活かす。
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 前日 | 夜早く移動 → 駐車場近くもしくは宿泊施設で寝て体力温存。 夜中の撮影に備えて軽食・撮影機材の準備。 |
| 撮影日 | 深夜2〜3時に起きて準備。 3〜4時頃、東の地平線近くが明るくなる前の時間帯に撮影スタート。 構図に前景をいれる場合は水平な場所・視界が開いている場所を選ぶ(例:正木ヶ原付近)。 明け方(日の出前後)の日出ヶ岳からの展望で「朝焼け+星残り」のショットも狙う。 朝日の撮影後、帰路またはその他ハイキングスポットを巡る。 |
星景写真に必要な装備と注意点
星景写真のクオリティは、機材と準備で大きく変わります。
カメラ・レンズ・三脚
- カメラ:高感度性能(ISO)に優れた一眼レフカメラやミラーレスカメラがおすすめ。
- レンズ:広角レンズ(焦点距離14〜24mm程度)が必須。F値の低い明るいレンズ(F2.8以下)だと、よりクリアな星を写せます。
- 三脚:長時間露光を行うため、しっかりした三脚は必須です。
- その他:予備バッテリー、レリーズ(リモートシャッター)、レンズヒーターなど。
寒さ・雨対策の服装
標高が高いため、夏でも気温が急降下することがあります。防寒着(ダウンジャケットなど)、手袋、帽子は必ず持参しましょう。また、突然の雨に備えて防水・防風のウェアも欠かせません。
夜間登山に必要な装備
- ヘッドライト:2つ以上あると安心です。
- 登山靴:足元の悪い場所も多いので、しっかりとした登山靴を選びましょう。
- 熊対策:大台ヶ原は熊の生息地です。熊鈴やラジオなど、音を出すものを身につけましょう。
撮影後の疲れを癒やす:近隣の温泉施設ガイド
冷えた体を温め、撮影の疲れを癒やす温泉は欠かせません。大台ヶ原周辺には、撮影のついでに立ち寄れる魅力的な温泉施設がいくつかあります。
- 入之波温泉(しおのはおんせん)山鳩湯:大台ヶ原から車で約40分。秘湯感あふれる温泉で、濁り湯が特徴です。星空撮影の疲れを癒やすのにぴったり。
- 洞川温泉郷(どろがわおんせんごう):大台ヶ原から車で約1時間半。レトロな街並みが魅力で、温泉旅館や日帰り入浴施設が点在しています。
- 宮の湯:大台ヶ原から車で約1時間20分。単純硫黄泉で、美肌効果も期待できる温泉です。
大台ヶ原で星景撮影を成功させるためのポイントまとめ
大台ヶ原の星空は、ただシャッターを切るだけでは思うように撮れません。自然条件や時間管理を工夫することで、ようやく理想の星景写真が撮れるのです。最後に、撮影を成功させるためのポイントを整理しておきます。
- 月齢と月没のチェックは必須
満月に近い時期は夜空が明るすぎて天の川が見えません。新月期や月没後の時間帯を狙いましょう。 - 天気予報は“複数サイト”で確認
特に夜間から明け方の雲量予報は重要です。一つの予報だけを信じず、複数の情報を照らし合わせましょう。 - 前泊や車中泊で時間を確保
星空撮影は深夜〜早朝に及びます。無理のないスケジュールを組むためにも、宿泊を計画に入れるのがおすすめです。 - 光害の少ない方向を選ぶ
大台ヶ原は南側に海や山が広がっており、比較的人工光が少ないのが魅力。撮影構図を工夫すれば、街の明かりを避けて星を引き立てられます。 - 昼間の下見は欠かさない
夜は足元が見えにくく、撮影ポイントを探すのも困難です。安全性や前景の構図を事前に確認しておくことで、夜の撮影がスムーズになります。 - 防寒・防湿対策を忘れずに
標高の高い大台ヶ原では夏でも冷え込みます。さらに夜露で機材が結露することもあるため、防寒着とレンズヒーターや乾燥材を準備しましょう。 - 余裕を持った行動を心がける
登山道を歩く時間や撮影の試行錯誤で、予定より時間がかかることも。焦らず楽しめるように、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
大台ヶ原を楽しむための外部リンク集
大台ヶ原ビジターセンター公式サイト:登山道や気候の情報、最新のイベント情報をチェックできます。
GPV気象予報:星景写真の撮影に欠かせない、雲や風の動きを予測できる専門の気象予報サイトです。
月齢カレンダー:新月の日をチェックし、計画を立てるのに役立ちます。


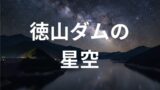


コメント